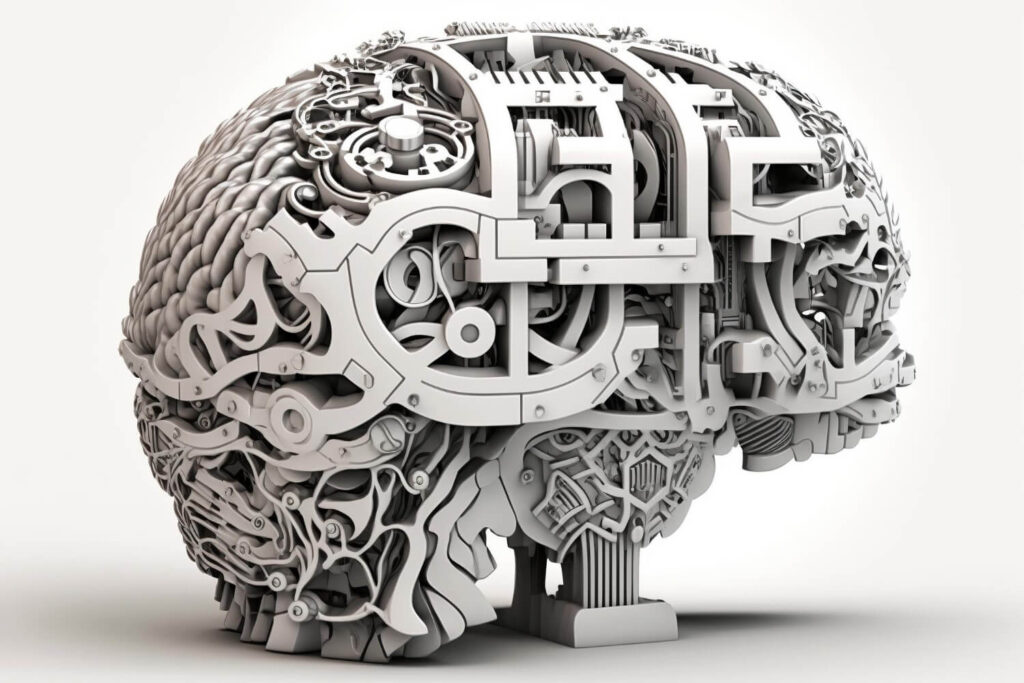高性能・高品質なPCが、一般市場に出回るようになって久しい今日この頃ですが、近頃「生成AI(Generative AI)」なるものが世間を大いに賑わしています 。
そしてかの中国では、そもそもAIのみならず、様々なIT関連テクノロジーが、モノによっては他国を凌駕するほど普及や開発が進んでおり、正に脅威となっております。
例えば、 加速度的に中国国内で普及したAlipayやWeChatPayを始めとする、QRコード決済を始めとするモバイル決済技術。通信技術、ビッグデータ取引技術、半導体の生産技術など、多様な分野のテクノロジーが、割と世界をリードするようなイイ感じに目立つようになってまいりました。
かつては安価で低品質の商品が量産されるイメージが強かった中国製品ですが、今や革新的な技術が開発され、なおかつ間髪入れぬ実用化で世界を驚愕させるようになってきました。
その躍進の背景には、国家レベルでの支援政策や巨大市場の存在、さらにはITベンチャー企業群の台頭など、様々な要素が絡み合っていると言われています。
本記事では、中国のIT技術が、具体的にどの程度まで進んでいるのかを、ゆっくりしていってね!で掘り下げていきたいと思います。
目次
人工知能(AI)技術の驚異的な進化について
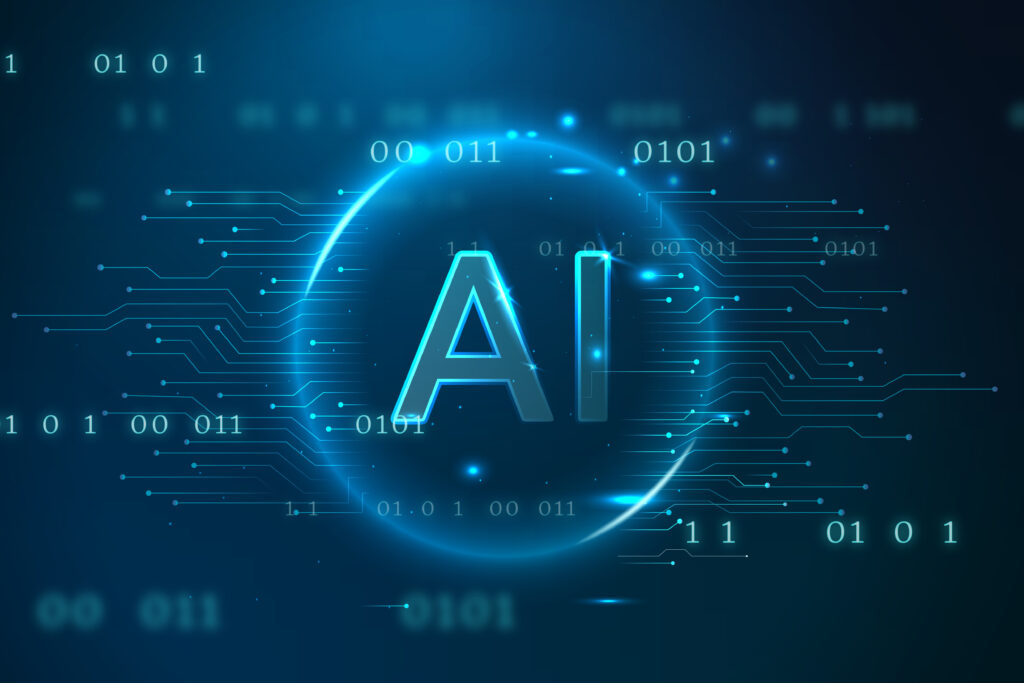
中国政府は2017年7月に、新たな国家戦略として「AI2030」を発表しました。 これは、AI産業の発展に向けた戦略目標であり、2030年に中国のAI産業を世界トップ水準に向上させる計画です。
「AI2030」では3段階の目標で進められます。
第1段階
2020年までにAIの技術・応用を世界の先進水準に引き上げて、規模は1兆元(約16兆円)を目標とします。
第2段階
2025年までにAIの基礎理論と一部のAI技術・応用を世界トップ水準まで向上させます。規模は5兆元(約81兆円)を目標とします。
第3段階
2030年までにAI理論・技術・応用の全てを世界トップ水準とし、また中国が世界の「AI革新センター」になることを目指します。規模は10兆元(約162兆円)を目標とします。
2030年までに、中国が世界のAI世界の中心で、愛をさけぶことを目標に掲げた、非常に大胆かつ戦略的でパワフル&ナイスな計画です。既にその成果は着々と現れており、特に顔認証や自動運転、自然言語処理などの分野でめざましテレビな進歩が見られます。つい最近も中国産生成AI「DeekSeek」が大きな話題になりましたよね。
中国の街中には、いまや無数の監視カメラが設置され、膨大なデータをAIがリアルタイムで処理して犯罪抑止や安全管理に利用されており、夢のようなディストピアが構築されています 。
そして、大手IT企業の「テンセント」が提供する顔認証サービスや、「アリババ」が提供する顔認証サービス「支付宝(アリペイ)」は精度が高く、コンビニの支払いや本人確認、施設の入退場管理に至るまで、広範囲に活用されています。
また、自動運転の分野に於いては、中国で最大の検索エンジンを提供する、IT大手の「百度(Baidu)」は「Apollo計画」と名付けた自動運転プラットフォームを推進しており、米国の「Waymo」や「テスラ」と並んで、自動運転テクノロジー開発の最前線に立っています。
既に中国国内では、実際に自動運転タクシーの商用サービスが開始されていることからも、そのレベルの高さがうかがえます。まあ、壮大な人体実験の犠牲に伴う事故データ集約により、技術開発が成り立っているなんて揶揄する人もいますが、まああながち間違っていないかも(←問題発言。もう筆者は中国に入国出来ないかもつД`)グスン)
キャッシュレス社会に於けるモバイル決済の普及

中国では、すでに現金をほとんど使わないキャッシュレス決済の社会が実現しています。
一般社団法人キャッシュレス推進協議会が公表した、2022年の世界主要国におけるキャッシュレス決済比率によると、中国は韓国に次いで2位の83.5%でした。凄い!ちなみに日本はたった36%で残念過ぎます。 しょぼい!
中国では、主にアリババ傘下の「支付宝(アリペイ)」とテンセント傘下の「WeChat Pay」が、主なプラットフォームとなっております。
利用者はスマートフォンのQRコードをスキャンするだけで、一般のお店だけでなく、屋台での食事やショッピング、公共交通機関、医療費や公共料金まで、モハメドありとあらゆる支払いを瞬時に完了できるので、若者を中心に、現金やクレジットカードを持ち歩く習慣が、ほぼ無くなったと言われています。
モバイル決済が普及することにより、消費行動のデータが蓄積され、マーケティングや金融サービスだけでなく、、かの悪名高き「社会信用システム」の構築などにも寄与されており、このようなキャッシュレス社会の実現スピードと浸透度は、世界的に見ても圧倒的な水準に達しています。
次世代通信(5G・6G)技術の開発

通信インフラの分野でも中国の躍進は明白でです。
特に第5世代移動通信(5G)の普及に関しては、世界最多の基地局数を誇り、2024年12月の時点で、 約410万局に迫る勢いで日々設置が進んでいます。5G接続数は2024年末に10億超を超える様です。凄っ!
「ファーウェイ(Huawei/華為)」や「ZTE」などの中国企業が、5Gインフラの主要な提供企業として世界中で存在感を示しています。ただし、米中貿易摩擦の影響でファーウェイ製品の海外展開には障害が生じているものの、中国国内では広く普及しております。
さらに中国は更にその先の6G研究にも積極的です。
中国の「国家6G技術研究開発推進作業組(中国科学技術部など複数の省庁によって構成)」は「6Gネットワークアーキテクチャの展望」と「6G無線システムの設計原則と典型的な特徴」などの技術方案を発表しました。これは、「IoE:Internet of Everything(あらゆる物事のインターネット/すべてのインターネット。モノだけではなくヒトやサービスも含めたすべてがインターネットにつながること)」から、「あらゆる物事のAIインターネット(AI+IoT)」への技術的道筋を提供するものです。6G技術の商用化の目途は、おおむね2030年になるようです。
2030年前後の導入を視野に入れ、通信速度の更なる高速化や、超高解像度データ通信、衛星通信まで、次の時代の通信基盤のリーダーシップを狙っていると言われています。
独自技術の追求と半導体分野での挑戦について
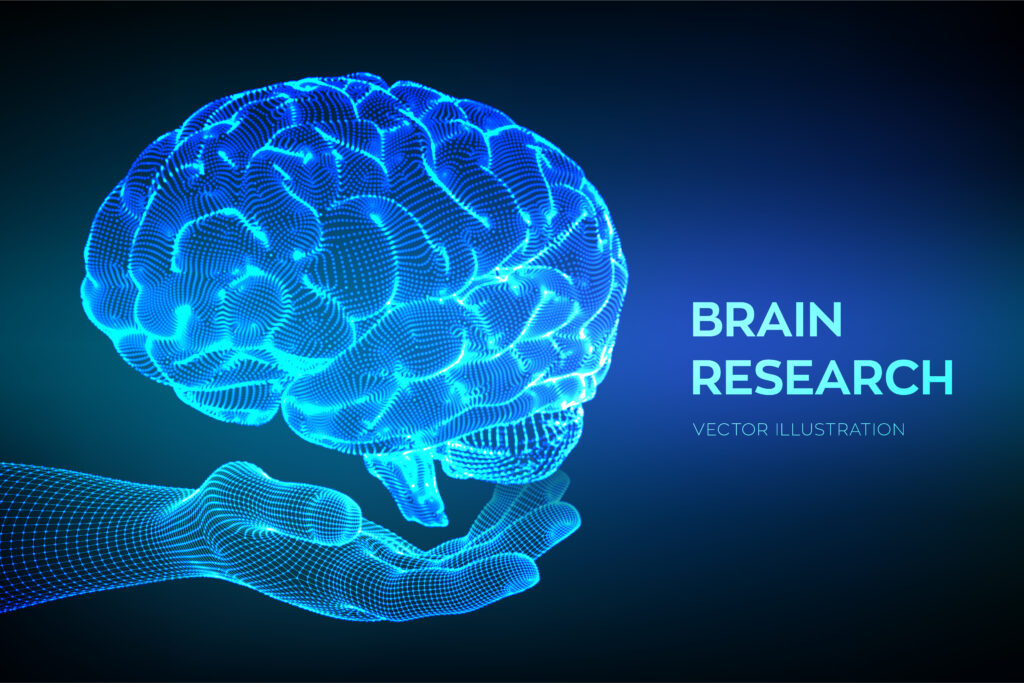
一方で、半導体技術では課題も指摘されてきました。米中の対立を背景に、アメリカは中国への先端半導体や製造設備の輸出を厳しく制限してるのは周知の事実です。このため、中国では、AIや5Gなどのテクノロジーを支える、半導体の国内生産体制の構築が急務となりました。
中国政府は現在、国内IT企業各社に、大規模な補助金や税制優遇策を用意し、半導体企業の育成に注力しております。特に「中芯国際集成電路製造(SMIC/Semiconductor Manufacturing International Corporation)」を中心に、先端的な半導体製造技術の開発が加速しています。ただし、世界最先端の技術であるEUV(極端紫外線露光)技術などについては、現時点でEUV露光装置を実用化できたのは露光装置世界最大手のオランダのASMLしかなく、結果、依然として西側企業が大きくリードしている状態です。
とはいえ、半導体の設計(ファブレス)企業では、中国の成長は著しいようです。例えば「ファーウェイ(Huawei/華為)」傘下の「ハイシリコン・テクノロジー(HiSilicon Technology、海思半導体)」などが、自社スマホ用に高性能チップを次々と開発を始めました。今後、半導体分野での独自技術の確立がどの程度実現するかが、中国IT産業全体の未来を左右する鍵になりそうです。
まとめ

このように、中国のIT技術は、AI、モバイル決済、通信技術など多くの分野で世界的にも最前線に立ち、実用的かつ普及スピードが速く、劇的な進化を遂げています。しかしその一方で、半導体技術の自主開発などではまだ克服すべき課題がいくつか存在します。
今後、中国のIT技術がどこまで世界を変えていくのか注目です。その結果、全世界の政治、経済、外交、安全保障に至るまで、あらゆる面に於いて世界に影響を及ぼす可能性が高くなります。中国の今後の動向を見守ることで、我々も世界に対する次の展開を読み解くヒントが見えてくるのかもしれません。
参考文献
グローバルコンパス/【2025年版】中国のキャッシュレス決済の現状は?Alipay/WeChatPayの登録&利用方法も解説
野村資本市場研究所/新展開を迎える中国のビッグデータ取引をめぐる動向
日経BP綜合研究所/特許が世界の42%を占める 中国の5Gが加速
ai2030.org
三井住友DSアセットマネジメント/世界No.1を目指す中国の『AI2030』戦略【キーワード】
SciencePortalChina/テンセント、顔認証技術を強化
SciencePortalChina/支付宝が顔認証システム導入 うなずくだけでログイン可能
自動運転ラボ/百度(Baidu)の自動運転戦略(2023年最新版)
SONPOインスティチュート・プラス/中国の自動運転タクシーの実情に迫る/北京レポート(1)
~安全配慮で運行エリア制限、今後はインフラ協調でエリア拡大へ~
Wikipedia/社会信用システム
新華網日本語/中国の5G基地局、410万カ所超す
日経クロステック/「中国5G接続数は2024年末に10億超へ」GSMA調査、利用格差は著しく縮小
CRIOnline/中国で6G技術の商用化 ほぼ2030年に確定
日立ソリューションズ・クリエイト/IoEとは? その概要とIoTとの違いなど
note/6Gとは?~特徴と今後の展望について~
中央日報/中国チャイナ・モバイル、世界に先駆けて6G通信テスト用衛星を打ち上げ
日経XTECH/米制裁下でも内製化に挑む中国半導体、2025年注目の5社を分析
東洋経済オンライン/中国半導体「SMIC」に最先端設備の調達リスク
TELESCOPE MAGAZINE/半導体の微細化に不可欠なEUV露光技術の現状とこれから
日経TECH/「心臓」を押さえた中国メーカー、スマホ半導体はもはや世界トップ