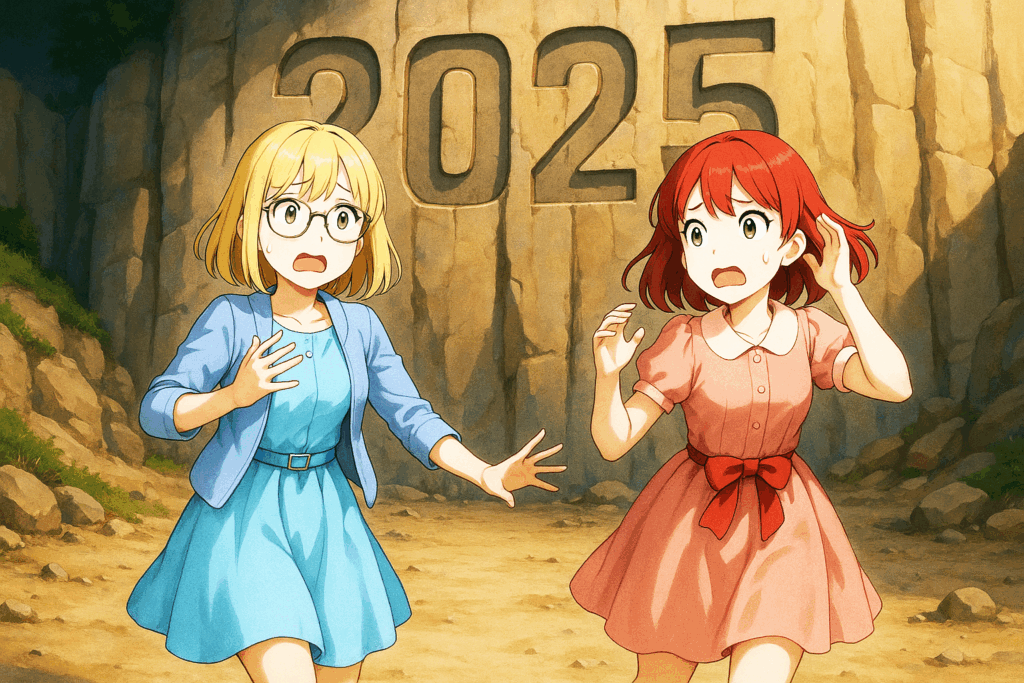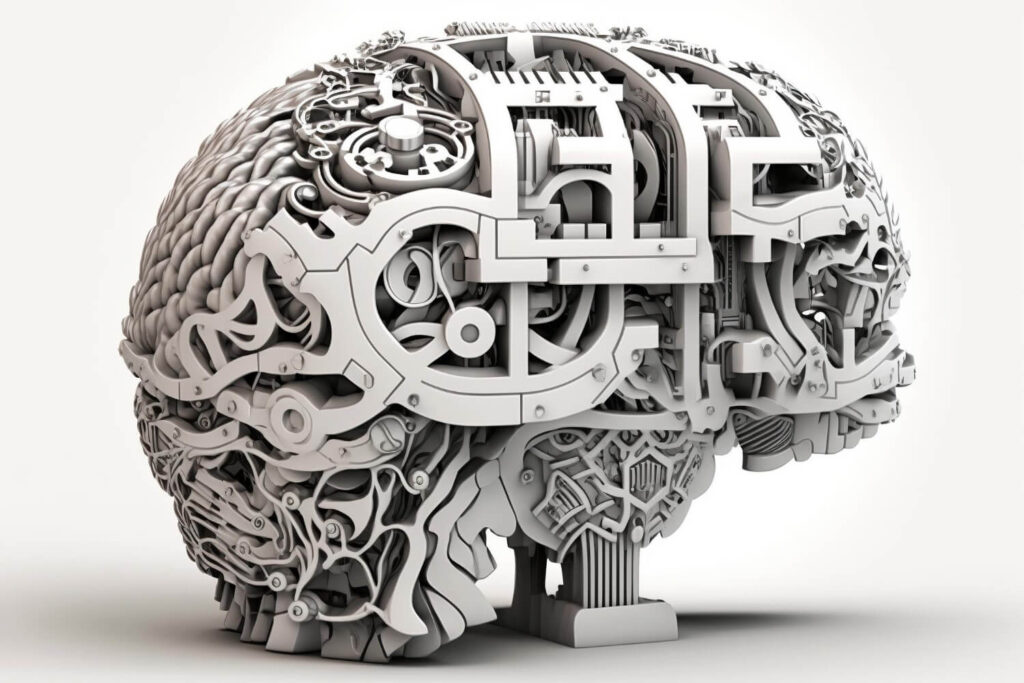高性能・高品質なPCやスマートデバイスが、一般市場に出回り、誰もが気軽にITに触れられる機会が多くなってしまい、2025年もすでに入って久しい今日この頃ではありますが、ここ最近、「2025年の崖」というキーワードを耳にしたり目にしたり、舌で味わったりしたことはないでしょうか。
全く知らないという人も、今回を契機に覚えておくと何かの役に立たないかもしれません。ちなみに「壁」じゃなくて「崖」です。筆者もつい最近まで間違えてしまっておりました。反省。
「2025年の崖」とは、日本企業のITシステムがこれから、もしくはもう直面する重大なリスクを指す言葉です。
経済産業省が2018年に公表した「DXレポート」で初めて使われた用語であり、多くの企業に「レガシーシステム(古い基幹システムの事。昔、会社でオーダーメードで作ったり、既製品のソフトを買ってずーっとそのままで使ったままでいること)が残ったままでは、これまででも4超円/年の経済損失が存在していたというのに(そっちの方を早くなんとかしろよ、とは思いますが)、2025年以降は、これまでの約3倍の、毎年最大で12兆円もの経済損失が発生しちゃうぞ、どうするんだいベイビー(©花輪くん)、と警告されてしまっています。どうしよう。
同レポートによれば、2025年には企業の基幹システムの約6割が、導入から21年以上経過する見込みなので、老朽化したシステムをそのまま放置しておいたら、正に「崖からコロリころげた木の根っ子」になってしまい、巨額の損失を招いてしまう、どうしよう。という意味で「2025年の崖」と名付けられました。
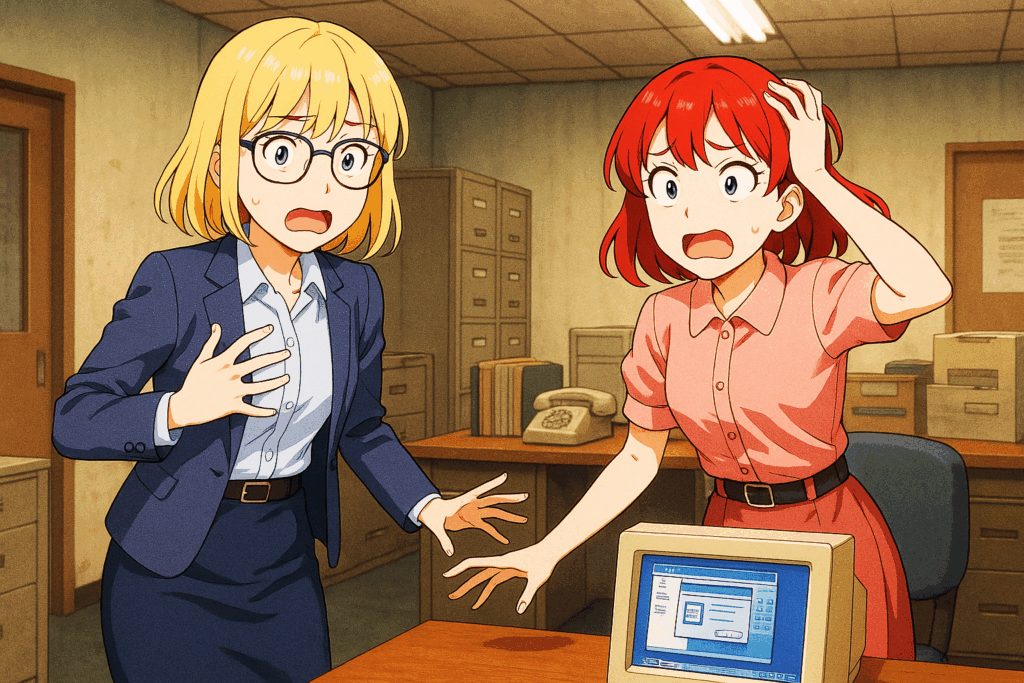
ようするに、「2025年」というのは、あくまで象徴的な表現であり、本質としては、「レガシーシステムの問題がピークに達し、何も対策をしなければ企業の競争力や業績が急落しかねない」という危機感を表現した言葉、という訳です。
では、なぜあえて「2025年」をキーワードとして使っているのかと言うと…。
用語の背景には、2000年前後に多くの日本企業が導入した基幹システムが、2025年前後にサポート期限や寿命を迎えるタイミングになることが挙げられます。
例えば、かつて2025年にサポート終了予定(その後2027年に延長)だった、SAP社が提供するERPソリューション「SAP ERP (経理・財務、人事、製造、調達・購買、サプライチェーン、販売など、企業の事業運営に必要なコアなプロセスを、単一の統合システムで管理することができてしまう、筆者は使ったことはないけれど、おそらく超便利なシステム)バージョン6.0」以前のバージョンの保守サポートが終了する!…といった問題が顕著化してきたことが一つの契機となりました。
その「2025年の崖」という、つおいパワーワードは、企業に強いドットインパクトとトラウトを残し、見てみなかったふりをする…ことはなく、今後は「デジタルトランスフォーメーション(DX)」が必須だだだ!という風潮に流れていく世の中を象徴する言葉となりました。
「デジタルトランスフォーメーション(DX)」とは、デジタルテクノロジーを使用して、ビジネスプロセス・文化・顧客体験を新たに創造(あるいは既存のそれを改良)して、変わり続けるビジネスや市場の要求を満たすプロセスの事を言います。もっと簡単に説明すると、コンピューターを使って何だか超イ~イ感じに仕事に活用していこうぜぃ、という概念です。
目次
日本企業やIT業界が直面する課題について
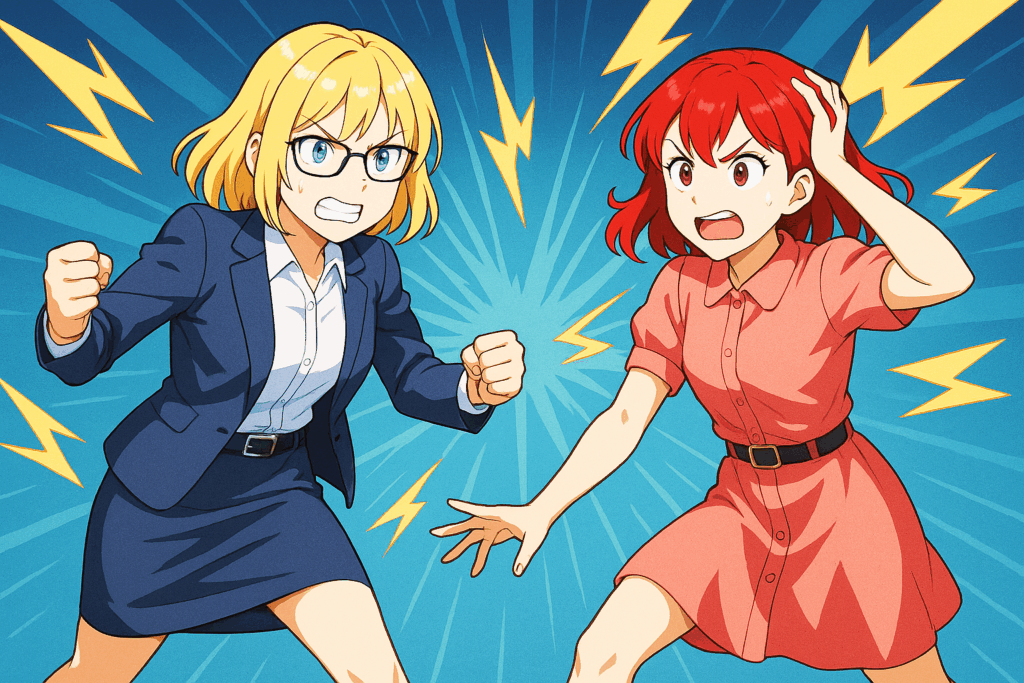
「2025年の崖」が指摘する主な課題には、企業内に残るレガシーシステムの老朽化・複雑化以外にも、それを支える人材の不足があります。長年使われてきた基幹システムはブラックボックス化し、システムの中身が一部の社員にしか分からない状態になっています。ちなみに鉄人28号の敵役はブラックオックスです。
ITに詳しい社員に何でもかんでも押し付けて、オリジナルシステムを作らせたり、ベンダーとの面倒な交渉事を一人でやらせた後に、その社員がふざけんな、と会社を辞めてしまった、さあ大変、なんてケースなんて、よくある話です。どこか既視感があると思ったら、筆者がまんまその状況でした。出ていった側と残された側両方経験しております。
まあ、ようするにその結果、自社で柔軟に改修できず、新しい技術との連携も難しく、業務の非効率を招いていて、会社的には自業自得の状態です。
さらに深刻なのは、そんなイレギュラーな状況も関係なしに、ふつーにこのようなレガシーシステムを維持してきた熟練エンジニアが定年を迎えてしまい、属人的な「暗黙知」や「ノウハウ」が失われつつあることです。
そもそもエンジニアや職人、漫画家やITライターみたいな人種は、自分が長年かけて築いてきたノウハウなんて簡単に他人には公開しないもの。寿司職人の「見て覚えろ」みたいなもんですな。非常に醜悪ではありますが、業が深い世界なので仕方がありません。特に会社や同僚、部下との関係性がさほど良くないのであれば、何も伝えずにシレっと定年で辞めてしまうなんてことは良くある話だし、私でも以前の会社で定年迎えていたらそうしていたかもしれません。今の会社には恩義ありますので、そんなことしませんけどね。
レガシーシステムのブラックボックス化は、まさにそうしたベテランIT人材の引退によって、知見が継承されずに、どうしようもない状況になっている現状に起因しています。 ちなみに鉄人28号の敵役はブラックオックスです。
また、これは世の中全業種にも言えることではありますが、IT系人材の絶対的な不足も大きな問題です。経済産業省の予測では、2025年までに日本のIT系人材が、約43万人不足するとされています。よ、よ、よ、43万人~?
圧倒的人手不足!
人手不足のために、システム刷新プロジェクトを担う人材が確保できず、結果として老朽化したシステムをずっと使い続けざるを得ない企業も増えると懸念されています。
このような状況では、新規開発やDX推進に十分なリソースを割けず、デジタル化の遅れがさらに進んでしまうのは必至です。
また、数多くの企業でシステム投資が後回しにされてきたことも問題です。
老朽化したシステムの維持運用に多大なコストがかかる一方、その置き換え(リプレース)には巨額の投資と長い時間、そしてリスクが伴うため、意思決定が先延ばしになりがちでした。
会社の経営層なんて、自分が現役の時だけ無事に乗り切れれば良いのですから、将来を見据えたレガシーシステムのリプレース問題を十分に認識していないケースや、確かに費用対効果を試算するのが難しくて不透明なため、とりあえずIT予算を抑制して、おひとり様情シスを増やしてきたケースなんて、あるある大事典です。
その結果、既存システムの老朽化と人材不足の問題が一層深刻化しているのです。愚かですねえ。
代表的な企業の対応事例
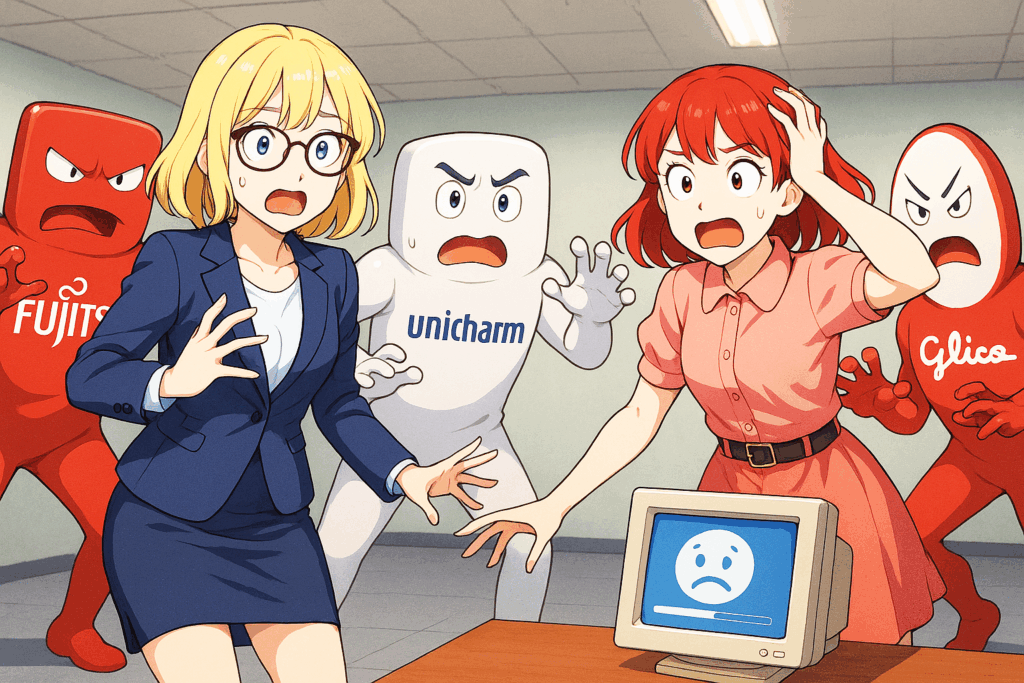
この危機感を受け、多くの日本企業が「2025年の崖」に備えた動きを始めています。
例えば富士通は2022年にメインフレーム(汎用機)事業からの撤退を表明し、自社および顧客の大型基幹システムをオープンなプラットフォームへ移行する流れを加速させました。「ブルータスお前もか」じゃないですけど、「富士通、お前もか」ですよね。ついに撤退するんかーい!と、最初ニュースを聞いた時衝撃的でしたねえ。
また、メガバンクや大手製造業でも、数十年稼働してきた勘定系や生産管理システムを新しい基盤へ刷新し、障害の多かった旧システムから脱却しようとするプロジェクトが進んでいます。
しかしシステム刷新は一筋縄ではいかない難題でもあります。実際、大手食品メーカーの江崎グリコや生活用品メーカーのユニ・チャームでは、新たな基幹システムへの切替え時に不具合が生じ、製品の出荷遅延などのトラブルが話題になりました。みずほ銀行なんか、2025年問題が起きる前からシステムトラブルだらけですしね。
これらの例は、レガシーシステムからの移行が如何に技術的・業務的にいかに複雑かを物語っています。
新システム導入には業務プロセスの見直しや入念なテストが不可欠ですが、スケジュールや予算の制約からトラブルが発生するケースが多々あります。新システム導入って、ホント何が起きるか良く分からんのですたい。ユーザーも、こちらの予想しない使い方をしてシステムをぶっ壊す場合もあるしね…。いやはや。
一方で、DXの取り組みに成功し競争力を高めている企業も一応存在します。
例えば、小売業では在庫管理や顧客データを統合して需要予測にAIを活用する、製造業ではIoTで工場設備の稼働データを分析して予防保全に役立てる、といった先進事例も報告されています。
生産性低下と国際競争力への懸念について
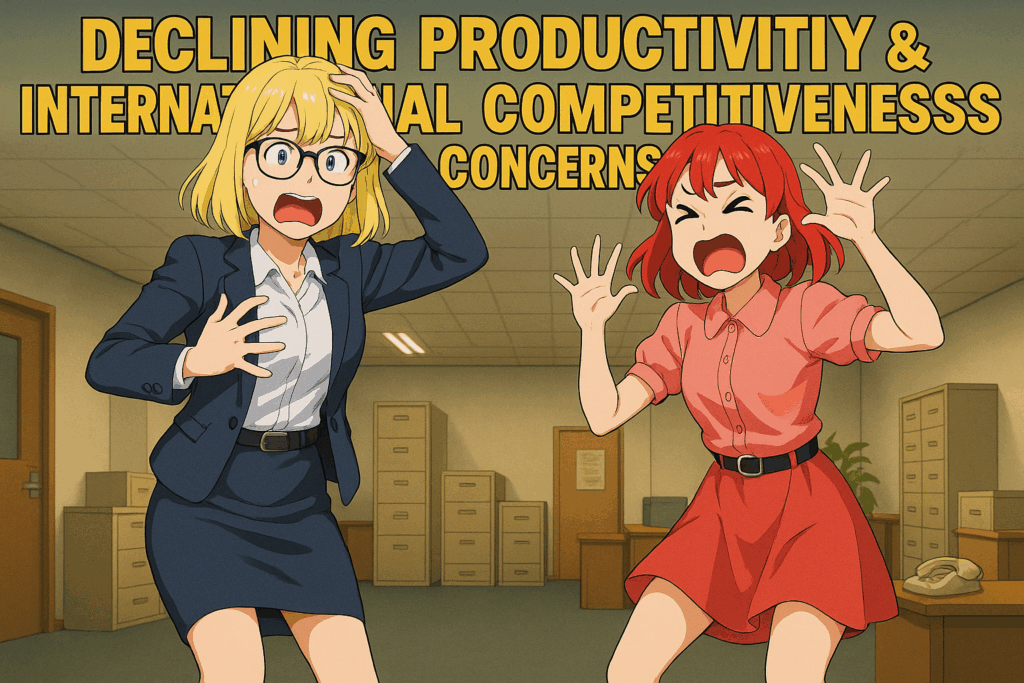
「2025年の崖」による影響は、日本経済全体に大打撃となり得ます。
老朽化したITシステムに足を引っ張られて業務効率が低下すれば、生産性の伸び悩みにつながるのは間違いないでしょう。実際、レガシーシステムがこのまま残り続ければ、業務改善やDX推進が妨げられ、企業は競争力低下やリソース不足に陥る恐れがあると指摘されています。
国際的に見ても、日本企業のデジタル化の遅れは、海外と競合するにあたって、不利な状況を生み出しかねません。DXの遅れによって市場の変化に素早く対応できなければ、ビジネスチャンスを逃し、グローバル競争で後れを取ってしまう可能性があります。 なんといっても経済産業省が試算した「最大年間12兆円の経済損失」という数字は、日本企業がデジタル競争で敗北した場合のインパクトを物語っています。非常に重いキーワードですよね。
その12億円の詳しい内訳を、経済産業省は明らかにしていませんが、おおむね
・ITシステム障害による業務停止
・データ活用の遅れによる機会損失
・非効率な業務プロセスにかかる余計なコスト
なんだろうなあ、と損失の要因は色々と考えられます。
これだけの経済的ダメージは、各個別の企業のみならず、サプライチェーン全体や日本全体にも影響を及ぼすに違いありません。
一方で、2025年の崖を乗り越えてDXを実現できれば、こうした損失を回避できるだけでなく、新たな価値創出や国際競争力の強化によって経済成長を牽引することも期待できます。
「諦めたらそこで試合終了ですよ」
デジタル庁の設立、中小企業支援などについて
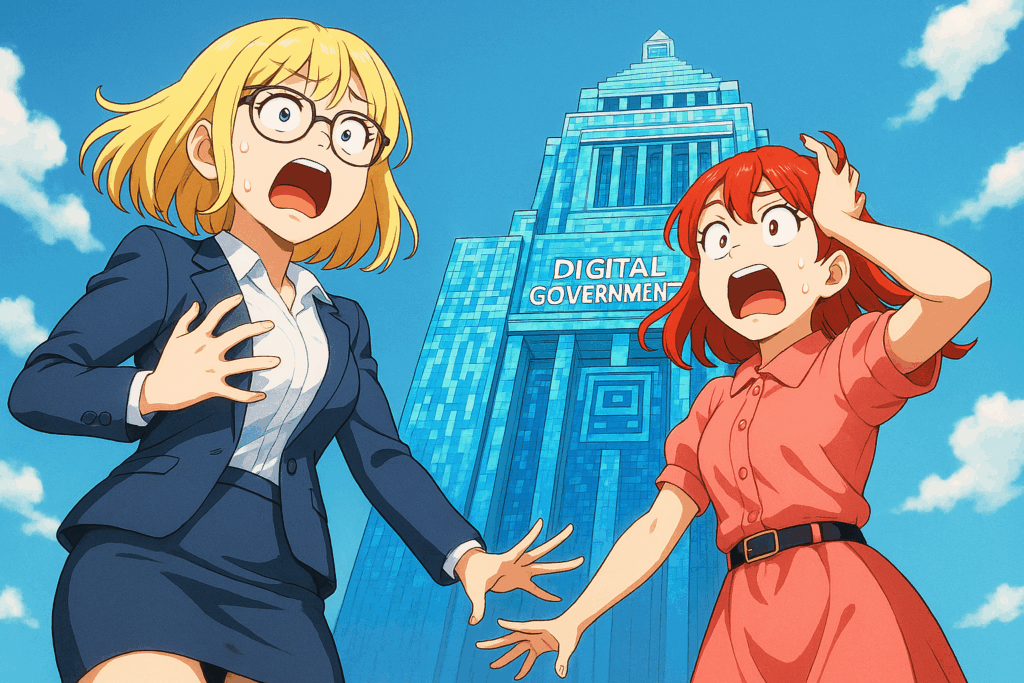
日本政府もこの課題に対応すべく、様々な施策を講じています。
象徴的なのはデジタル庁の設立です。デジタル庁(でじたるちょう、英: Digital Agency)は、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け、その行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを目的として内閣に置かれる省庁であり、2021年9月1日に発足しました。
デジタル庁は、縦割りだった各省庁のIT政策を統合し、日本全体のデジタル化を推進する司令塔として位置づけられています。
例えば、行政サービス自体のデジタル化(例:河野太郎さんでおなじみの「ハンコ廃止」やオンライン手続の促進)を進めることで民間企業のDXにも波及効果を及ぼし、国全体のデジタル基盤を底上げする狙いがあります。
ちなみに経済産業省は、企業のDX推進を支援するためのガイドライン策定や、DXに積極的な企業を評価する認定制度(「DX認定制度」や「DX銘柄」)の導入も行っていますので、ざっと目を通しておくと幸せになれるかもしれません。
これらについては、はデジタル化に取り組む企業を後押しし、経営層の意識改革を促す施策です。
また、特に 特に対応が遅れがちな中堅・中小企業向けには、「IT導入補助金」など金銭面の支援策や専門家派遣の制度も整備されています。例えば「中小企業デジタル化応援隊事業」では、中小企業がIT化・デジタル化に取り組む際に、登録IT専門家の支援を受けられ、その費用の一部について補助が行われています(現在、第二期は終了)。
こういった施策により、人材や資金に制約のある企業でもDXに踏み出しやすくし、日本全体で「2025年の崖」を乗り越えることを目指しています。
まとめ
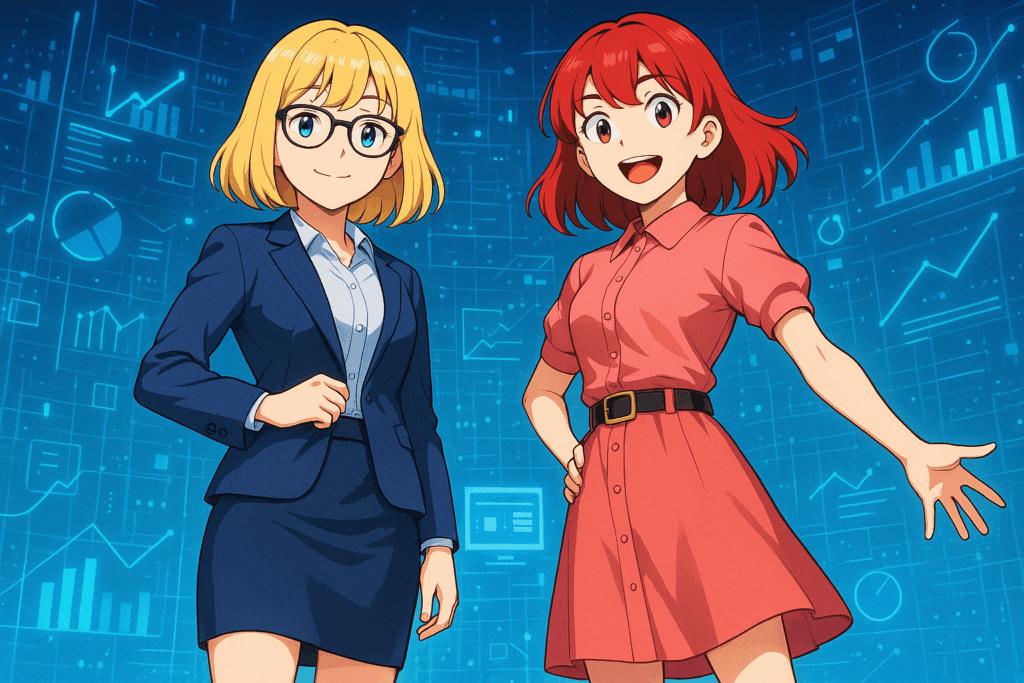
「2025年の崖」を克服し持続的な成長を遂げるには、企業と働くビジネスマンの力、その双方が協力しあい、混然一体となって、主体的に動く必要があります。まず経営層には、強いリーダーシップと明確な戦略ビジョンが求められます。トップ自らがDXの重要性を訴え、全社的な変革の方向性を示すことで、組織全体の意識改革が進んでいくことでしょう。
そして、限られたリソースの中でITシステムの刷新優先順位を付け、どのレガシーシステムから手を付けるかを見極めて、計画的にモダナイゼーション(近代化)を実行することが重要です。
現場のビジネスマンひとりひとりも、この問題を他人事とは捉えず行動することが大切です。
社員自らがデジタル活用のスキルを磨き、日々の業務の中で改善提案を行っていく姿勢が求められます。
例えば、普段の業務にRPA(定型業務の自動化ツール)を取り入れてみたり、基本的なデータ分析手法を学んで業務改善に活かす、といった取り組みなんかしてみては如何でしょう。RPAなんか結構敷居が低いですし。
ITに詳しくない人でも、簡単で小規模のデジタル化の積み重ねをしていくことが、結果的に大きな業務効率化につながり、DX推進の力となります。
企業は、人材面への投資を大々的に行う必要があります。有能な人材を採用し、社内研修や外部講座を通じてIT系人材の育成や社員のデジタルスキル向上に取り組み、DXを牽引できる人材を計画的に育成・確保する必要があります。
また同時に、既存のIT系人材が働きやすい環境を整え、筆者みたいな優秀な人材の流出を防ぐことも重要でしょう。
更に、程度の低いベンダーとはある時期から袂を分かち、専門性の高いベンダーやコンサルタントを探して、付き合っていくことが重要です。自社だけで難しい課題に対処するのではなく、外部の力を借りることでDXのスピードと成功率を高めることができます。
2025年という年度の節目は象徴的ではありますが、DXの道のりはその先も続いていきます。
今回の「2025年の崖」の騒ぎが、むしろ良い機会だったと思いなおし、この際、自社の課題を徹底的に洗い出して、できるところから改革に着手することが不可欠です。
今日の小さな一歩が、やがて大きな飛躍につながるでしょう。たぶん。きっと、いや、むしろ。
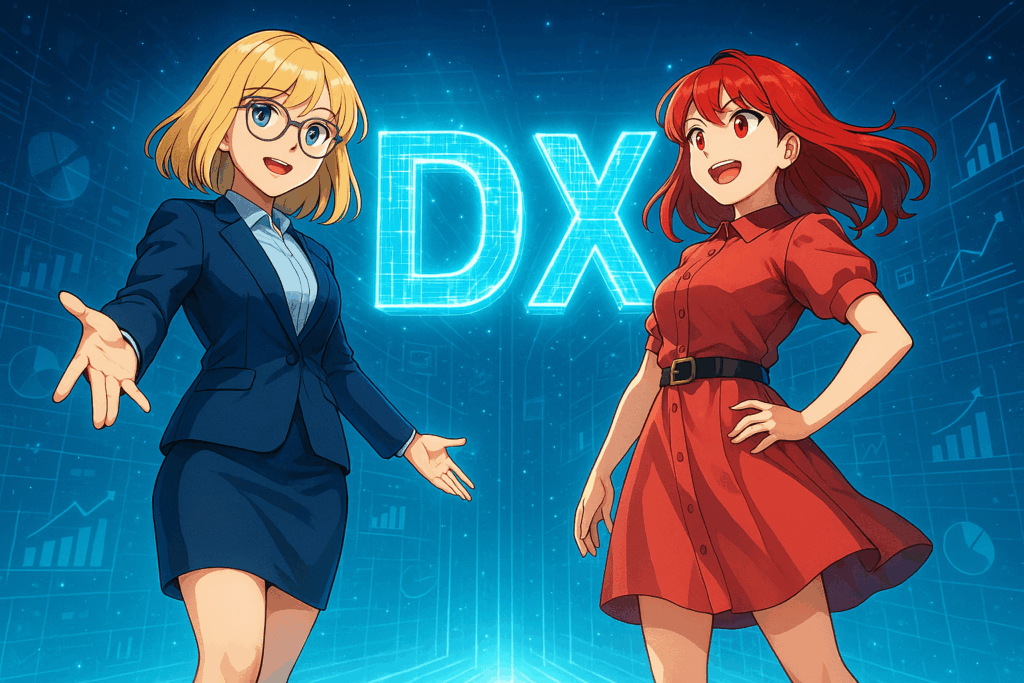
※生成AIでまんが投稿始めました
参考文献
経済産業省/デジタルトランスフォーメーション D X レポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開
SAP/SAP ERP とは
Wikipedia/デジタルトランスフォーメーション
ROBOT PAYMENT/「2025年の崖」とは?企業の課題と対策方法を解説
PERSOL/2025年の崖とは?定義や問題点・必要な対策をわかりやすく解説
Nomura System Corporation/経産省DXレポートの「2025年の崖」とは?問題点や対策をわかりやすく解説
docomo business/2025年の崖とは?現状の課題や対策を徹底解説
Deloitte/「2025年の崖」から転落しなかった企業がすべきこと
日経XTECH/グリコもユニ・チャームも苦渋、トラブル相次ぐERP導入に潜む大きな理解不足
CommercePick/ITシステム「2025年の崖」と江崎グリコやユニ・チャームの事例から見る基幹システムの移行問題
デジタル庁
Wikipedia/デジタル庁
Cross Marketing/デジタル庁とは?発足の背景や今後の施策を解説
DXPO College/2025年の崖問題とは?日本企業が直面する課題とその解決策
FUJITSU/モダナイゼーション 既存情報システムを最適化し、DX基盤としてのあるべき姿に
Wikipedia/ロボティック・プロセス・オートメーション